
「夜中に何度も目が覚める…」睡眠不足の原因と今すぐできる改善方法まとめ
夜中に何度も目が覚める、寝つきが悪い、朝起きても疲れが取れない睡眠の悩みを解決。睡眠の質を上げるための科学的根拠に基づいた改善方法、メラトニンの効果、生活習慣のコツまで専門的に解説します。
ドクターナウ編集部
2025.08.04
毎晩ベッドに入っても「なかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れない」といった悩みを抱えていませんか?実は、日本人の約4割が睡眠時間6時間未満という睡眠不足の状態にあります。良質な睡眠は、単なる休息以上の重要な役割を果たしています。この記事では、睡眠の基本的な役割から、睡眠の質が低下する原因、そして今日から実践できる改善方法まで、科学的根拠に基づいて詳しく解説します。
睡眠の役割と重要性

なぜ睡眠が必要なのですか?
睡眠は私たちの心身の健康維持に欠かせない生理機能です。眠っている間に、体と脳では以下のような重要な働きが行われています。
睡眠中、脳は日中に蓄積した疲労物質を除去し、記憶の整理と定着を行います。深い睡眠段階では、学習内容や体験した情報が長期記憶として保存されるのです。
睡眠中には成長ホルモンが活発に分泌され、細胞の修復や新陳代謝が促進されます。特に深夜1~3時頃に分泌のピークを迎えるため、この時間帯の良質な睡眠が重要です。
十分な睡眠により免疫細胞の働きが活性化され、感染症に対する抵抗力が向上します。睡眠時間が5時間未満の場合、風邪から肺炎に悪化するリスクが1.4倍に増加するという報告もあります。
睡眠が健康に与える影響とは?
| 睡眠の効果 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 認知機能の向上 | 集中力・判断力・記憶力の改善 |
| 情緒の安定 | ストレス軽減・うつ病予防 |
| 代謝機能の調節 | 体重管理・糖尿病予防 |
| 心血管系の保護 | 高血圧・心疾患のリスク低下 |
| 免疫力の維持 | 感染症予防・がん予防効果 |
睡眠が私たちの健康に与える影響は想像以上に広範囲です。
認知機能の向上では、深い睡眠中に脳内の老廃物が除去され、記憶の定着が促進されるため、翌日の仕事や勉強のパフォーマンスが大幅に改善します。
情緒の安定については、睡眠不足がストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を増加させるため、十分な睡眠により精神的な安定を保つことができます。
では、睡眠不足により食欲を抑制するレプチンが減少し、食欲を増進するグレリンが増加するため、適切な睡眠が体重管理の鍵となります。
心血管系の保護では、睡眠中に血圧や心拍数が低下し、心臓への負担が軽減されることで、長期的な心疾患予防につながります。
良質な睡眠は体の基本的な機能を正常に保つだけでなく、日中のパフォーマンス向上や病気の予防にも大きく貢献します。睡眠を「時間の無駄」と考えるのではなく、健康投資として捉えることが大切です。
適切な睡眠時間はどのくらいですか?
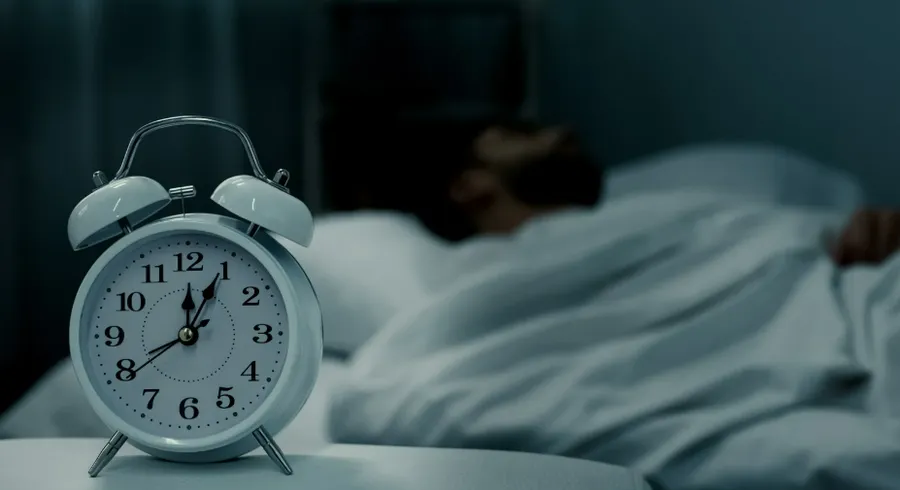
年齢別推奨睡眠時間
成人の適正睡眠時間は一般的に6~8時間とされていますが、年齢によって必要な睡眠時間は変化します。
| 年齢層 | 推奨睡眠時間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 18~25歳 | 7~9時間 | 成長期の終わりで十分な睡眠が必要 |
| 26~64歳 | 7~9時間 | 働き盛りで質の高い睡眠が重要 |
| 65歳以上 | 7~8時間 | 加齢により睡眠が浅くなりがち |
年齢によって必要な睡眠時間が変化する理由は、体の成長段階や代謝機能の変化にあります。
18~25歳の若年層では、脳の発達が完了する時期であり、学習能力や記憶力の向上のために長めの睡眠が必要です。この時期に睡眠不足が続くと、将来的な認知機能に影響を与える可能性があります。
では、仕事や家庭でのストレスが多く、質の高い睡眠による疲労回復が特に重要となります。この年代は睡眠時間を確保するのが最も困難な時期でもあるため、効率的な睡眠を心がける必要があります。
65歳以上の高齢者では、加齢に伴いメラトニンの分泌量が減少し、睡眠が浅くなる傾向があるため、睡眠環境の整備がより重要になります。
ただし、個人差があるため、日中に過度な眠気を感じず、心身の調子が良好であれば、その人にとって適切な睡眠時間と考えられます。
睡眠時間より重要な「睡眠の質」
睡眠時間を確保することも大切ですが、それ以上に重要なのが「睡眠の質」です。質の高い睡眠の特徴は以下の通りです。
- 寝つきが良い: 布団に入ってから30分以内に眠りにつける
- 深く眠れる: 夜中の覚醒回数が少ない
- すっきり目覚める: 朝の目覚めが良く、日中に眠気を感じない
質の高い睡眠を判断する3つの指標は、日常生活でも簡単にチェックできる重要なポイントです。
寝つきの良さは、日中の活動と夜間の休息のメリハリがついている証拠であり、適切な体内時計の働きを示しています。布団に入ってから30分以上経っても眠れない場合は、生活習慣や睡眠環境の見直しが必要かもしれません。
については、夜中に2回以上目が覚める場合は睡眠の質が低下している可能性があります。深い睡眠段階では成長ホルモンの分泌や記憶の定着が行われるため、この段階を十分に確保することが疲労回復には欠かせません。
すっきりとした目覚めは、睡眠サイクルが正常に機能している証拠であり、日中のパフォーマンス向上にも直結します。
睡眠時間を過度に延ばすよりも、これらの質的な要素を改善することで、より効果的な睡眠を得ることができます。睡眠の質を高めることで、必要な睡眠時間内で十分な疲労回復が可能になるのです。
睡眠の質が低下する主要原因

ストレスと精神的要因
現代社会では、仕事や人間関係のストレスが睡眠の質に大きな影響を与えています。
- 交感神経の過度な活性化により、リラックスできない状態が続く
- 考え事や心配事で頭が冴えてしまう
- ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌により、自然な眠気が阻害される
ストレス管理には、音楽鑑賞、読書、軽い運動など、自分に合ったリラクゼーション方法を見つけることが重要です。就寝前1時間は「リラックスタイム」として確保し、心を落ち着ける時間を作りましょう。
生活習慣の乱れ
不規則な生活リズムは、体内時計を狂わせる主要な原因です。
| 問題となる習慣 | 睡眠への影響 | 改善策 |
|---|---|---|
| 夜更かし・朝寝坊 | 体内時計の後退 | 毎日同じ時間の就寝・起床 |
| 昼寝の取りすぎ | 夜間の睡眠圧低下 | 昼寝は15時までに20分以内 |
| 夜間のスマホ使用 | メラトニン分泌阻害 | 就寝1時間前からデジタルデトックス |
| 夜間の明るい照明 | 体内時計の混乱 | 夕方以降は照明を段階的に暗く |
現代人の睡眠問題の多くは、生活習慣の乱れが根本原因となっています。
夜更かし・朝寝坊の習慣は、体内時計を1日24時間のリズムから徐々に後退させ、自然な眠気が遅い時間にしか訪れなくなります。特に週末の寝溜めは平日の睡眠リズムを大きく乱すため、可能な限り毎日同じ時間の就寝・起床を心がけることが重要です。
については、長時間の昼寝が夜間の「睡眠圧」を減少させてしまいます。睡眠圧とは起きている時間に比例して蓄積される眠気のことで、これが不十分だと夜になっても眠くならないのです。
夜間のスマホ使用は、ブルーライトによりメラトニンの分泌が抑制され、体が「まだ昼間だ」と勘違いしてしまう原因となります。
生活習慣の改善は一朝一夕にはできませんが、一つずつ着実に変えていくことで、睡眠の質は確実に向上します。まずは最も改善しやすい習慣から始めてみましょう。
睡眠環境の問題
睡眠環境は質の高い睡眠を得るための基本的な要素です。
- 春・秋: 18~22℃
- 夏季: 26℃以下
- 冬季: 15~18℃
- 湿度: 通年50~60%
外部の騒音や家族の生活音は、睡眠の質を大きく左下させます。耳栓の使用や、防音効果のあるカーテンの設置が効果的です。
夜間は可能な限り暗い環境を作ることが重要です。街灯や電子機器のLEDライトも睡眠に影響するため、遮光カーテンやアイマスクの利用を検討しましょう。
快適な睡眠環境を整えることで、自然と深い眠りにつきやすくなり、夜中の覚醒回数も減少します。環境改善は投資効果の高い睡眠改善方法の一つです。
カフェインやアルコールの影響
嗜好品の摂取タイミングと量は、睡眠の質に直接的な影響を与えます。
カフェインの覚醒作用は摂取後30分~1時間でピークとなり、効果が半減するまで2.5~4時間かかります。夕方以降のカフェイン摂取は寝つきを悪くし、眠りも浅くするため避けましょう。
お酒は一時的に眠気を誘いますが、体内でアセトアルデヒドに分解される際に、深い眠りが減少し浅い眠りが増加します。また利尿作用により夜中の覚醒回数も増えるため、寝酒は睡眠の質を低下させる原因となります。
飲酒は就寝3時間前まで、カフェインは午後3時以降は控えることで、睡眠への悪影響を最小限に抑えることができます。
睡眠の質を高める生活習慣とコツ

朝の習慣で体内時計をリセット
良質な睡眠は朝から始まります。体内時計を正しくリセットすることで、夜の自然な眠気につながります。
起床後すぐに朝日を15~30分浴びることで、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌がリセットされます。メラトニンは朝日を浴びてから約14~16時間後に再び分泌が始まり、自然な眠気を誘います。
朝食は脳と体の体内時計を同調させる重要な役割を果たします。炭水化物、たんぱく質、ビタミン・ミネラルをバランスよく摂取することで、一日のリズムが整います。
日中の過ごし方のポイント
日中の適度な運動は、深い睡眠を促進する効果があります。週5日以上、1日30分程度の有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)を習慣化することで、寝つきの改善と睡眠の質向上が期待できます。
| 運動の種類 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 有酸素運動 | 深い睡眠の促進 | 就寝2時間前まで |
| ヨガ・ストレッチ | リラクゼーション効果 | 就寝1時間前まで可 |
| 激しい筋トレ | 体温上昇で覚醒 | 夕方までに実施 |
運動が睡眠に与える効果は、運動の種類とタイミングによって大きく異なります。
有酸素運動であるウォーキングやジョギングは、深部体温を一時的に上昇させ、その後の体温低下により自然な眠気を誘発します。また、適度な疲労感が深い睡眠段階を促進し、成長ホルモンの分泌も活発になります。ただし、就寝直前の運動は交感神経を刺激し、かえって寝つきを悪くするため、就寝2時間前までに終了することが重要です。
などの軽い運動は、副交感神経を優位にし、心身のリラクゼーション効果をもたらします。特に深呼吸を伴うヨガは、ストレス軽減と睡眠の質向上に効果的です。一方、
激しい筋力トレーニングは体温上昇と交感神経の活性化により覚醒状態を引き起こすため、夕方までに実施することが望ましいです。
昼間の眠気対策として昼寝を取る場合は、15時までに20分以内に留めることが重要です。これ以上長く寝てしまうと、夜間の睡眠に悪影響を与える可能性があります。
夜の準備で質の高い睡眠を実現
就寝1~2時間前に、38~40℃のぬるめの湯に15~20分ゆっくりと浸かることで、副交感神経が優位になりリラックス効果が得られます。入浴後の体温低下が自然な眠気を誘います。
- 読書: 軽い内容の本や雑誌
- 音楽: クラシックやヒーリング音楽
- アロマテラピー: ラベンダーやカモミールの香り
- 軽いストレッチ: 深呼吸と合わせて実施
就寝前のリラクゼーション活動は、一日の緊張を解きほぐし、睡眠モードへの移行をスムーズにする重要な習慣です。
読書については、推理小説やサスペンスなど刺激的な内容は避け、エッセイや詩集などの軽い内容を選ぶことがポイントです。読書により視覚を適度に疲労させることで、自然な眠気を誘うことができます。また、紙の本を使用することで、ブルーライトの影響も避けられます。
では、テンポがゆっくりで音量が一定のクラシック音楽やヒーリング音楽が効果的です。特に60-70bpm程度のゆったりとしたリズムは、心拍数を落ち着かせ、副交感神経を優位にします。
アロマテラピーでは、ラベンダーの鎮静効果やカモミールのリラックス効果が科学的に証明されており、嗅覚を通じて脳に直接働きかけます。
軽いストレッチは筋肉の緊張をほぐし、深呼吸により酸素供給を改善することで、心身ともにリラックス状態に導きます。
これらの習慣を組み合わせることで、心身ともにリラックスした状態で睡眠に入ることができ、深く質の高い眠りを得ることができます。
デジタルデトックスの実践
スマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、メラトニンの分泌を抑制し、体内時計を乱します。就寝1時間前からは電子機器の使用を控えましょう。
- 寝室には睡眠以外の目的で電子機器を持ち込まない
- 充電器は枕元に置かず、別の場所で充電
- 時計のデジタル表示も明るすぎる場合は隠す
デジタルデトックスを実践する際の具体的な方法は、段階的に実施することで習慣化しやすくなります。
電子機器の持ち込み禁止は、寝室を「睡眠専用の空間」として位置づけることで、脳に「この場所は眠る場所」という条件付けを行います。テレビ、パソコン、タブレットなどは寝室以外の場所で使用し、寝室では睡眠と関係のない活動を避けることが重要です。
については、枕元での充電は電磁波の影響や音による覚醒リスクがあるため、別室での充電を推奨します。どうしても近くに置く必要がある場合は、機内モードに設定し、通知音を完全にオフにすることが必要です。
時計の表示も意外に見落としがちなポイントで、明るいデジタル表示は夜中に目が覚めた際の再入眠を妨げる原因となります。アナログ時計の使用や、表示を暗くする設定の活用を検討しましょう。
デジタルデトックスを実践することで、自然な睡眠リズムを取り戻し、深い眠りにつきやすくなります。
睡眠に効果的な成分とアイテム

睡眠をサポートする栄養成分
必須アミノ酸の一種で、セロトニンを経てメラトニンの原料となります。朝食で摂取すると、14~16時間後に自然な眠気を誘います。
- 豊富な食材: 牛乳、チーズ、大豆製品、ナッツ類、卵
- 摂取のコツ: 朝食時に意識的に取り入れる
トリプトファンを効果的に摂取するためには、食材選びと摂取タイミングが重要です。
牛乳やチーズなどの乳製品は、トリプトファンの含有量が高く、朝食時に手軽に摂取できる優秀な食材です。特に温かい牛乳は、トリプトファンの吸収を促進し、カルシウムによるリラックス効果も期待できます。
大豆製品である納豆や豆腐は、トリプトファン以外にもビタミンB群や良質なたんぱく質を含み、総合的な睡眠サポートに役立ちます。
では特にアーモンドやクルミが効果的で、トリプトファンに加えてマグネシウムも含有しており、筋肉の緊張を和らげる作用があります。
卵は完全食品と呼ばれるほど栄養バランスが良く、トリプトファンの他にもビタミンB6を含むため、セロトニンの合成を効率的にサポートします。朝食での摂取が効果的な理由は、14-16時間後の夜間にメラトニンとして機能するためです。
睡眠の質を改善する効果が科学的に証明されているアミノ酸です。深部体温を下げることで、スムーズな入眠をサポートします。
- 豊富な食材: エビ、ホタテ、カニなどの魚介類
- 効果: 寝つきの改善、深い睡眠の促進
グリシンは睡眠の質改善において科学的に効果が証明されている数少ないアミノ酸の一つです。
魚介類に豊富に含まれるグリシンは、体内で深部体温を下げる働きがあり、これが自然な眠気を誘発します。深部体温の低下は、私たちの体が睡眠モードに入るための重要なシグナルであり、グリシンはこの生理的な過程をサポートします。
などの甲殻類は特にグリシン含有量が高く、夕食に取り入れることで就寝時の体温調節がスムーズになります。また、グリシンには中枢神経系の興奮を抑制する作用もあり、
寝つきの改善だけでなく、
深い睡眠段階の維持にも効果を発揮します。研究では、グリシンを摂取することで睡眠効率が向上し、翌日の疲労感が軽減されることが報告されています。
興奮した神経を鎮静化し、副交感神経を活性化させる効果があります。
- 豊富な食材: トマト、バナナ、玄米、ヨーグルト
- 作用: 精神の安定、リラクゼーション効果
GABA(ギャバ)は脳内で抑制性神経伝達物質として働き、興奮した神経を鎮静化する重要な役割を果たします。
トマトに含まれるGABAは、特に夕方以降の摂取で効果を発揮し、日中のストレスや緊張を和らげます。トマトジュースとして摂取する場合は、塩分の少ないものを選び、就寝2-3時間前までに飲むことが推奨されます。
は、GABAに加えてトリプトファンやマグネシウムも含有しており、総合的な睡眠サポート食材として優秀です。
玄米は白米よりもGABA含有量が高く、主食として継続的に摂取することで、日々のストレス軽減に役立ちます。
ヨーグルトなどの発酵食品は、腸内環境を改善し、腸で産生されるGABAの生成を促進する効果もあります。これらの食材を組み合わせることで、
精神の安定と
リラクゼーション効果をより効果的に得ることができます。
睡眠環境を改善するアイテム
質の高い睡眠のためには、体に合った寝具選びが重要です。
| アイテム | 選び方のポイント | 効果 |
|---|---|---|
| マットレス | 適度な硬さで体圧分散 | 腰痛予防、寝返りサポート |
| 枕 | 首のカーブに合う高さ | 首・肩こり軽減 |
| 掛け布団 | 軽量で保温性・通気性良好 | 体温調節、快適性向上 |
質の高い睡眠を得るための寝具選びは、個人の体型や好みに合わせることが最も重要です。
マットレスについては、硬すぎると体圧が一点に集中して血行が悪くなり、柔らかすぎると体が沈み込んで背骨のS字カーブが崩れてしまいます。理想的なマットレスは、仰向けに寝た時に背骨が自然なS字を保てる適度な硬さを持ち、体重を均等に分散してくれるものです。これにより腰痛の予防と、無理のない寝返りが可能になります。
は首の自然なカーブ(頸椎の前湾)を維持できる高さが重要で、一般的に仰向け寝では2-4cm、横向け寝では肩幅に応じて調整が必要です。高すぎると首が前に出て呼吸が浅くなり、低すぎると首の筋肉が緊張してしまいます。
掛け布団では、軽量でありながら保温性に優れ、湿気を外に逃がす通気性を持つものが理想的です。重すぎる布団は寝返りを阻害し、睡眠の質を低下させる原因となります。
- アイマスク: 光を完全に遮断し、深い眠りをサポート
- 耳栓: 騒音を軽減し、中途覚醒を防ぐ
- 加湿器: 適切な湿度維持で喉や鼻の乾燥を防ぐ
- アロマディフューザー: リラックス効果のある香りで入眠促進
睡眠環境を改善するグッズは、個人の睡眠の悩みに応じて選択することが重要です。
アイマスクは、街灯や電子機器のLEDライトなど、わずかな光でも睡眠に影響を受けやすい方に特に効果的です。完全な暗闇を作ることで、メラトニンの分泌が促進され、深い睡眠段階に入りやすくなります。素材は肌に優しく、圧迫感のないシルクや綿素材がおすすめです。
は、交通音や隣人の生活音が気になる環境で威力を発揮します。ただし、完全に音を遮断してしまうと目覚まし時計が聞こえなくなる可能性があるため、適度な遮音効果のものを選ぶことが大切です。
加湿器は特に冬季に有効で、適切な湿度(50-60%)を維持することで、喉や鼻の乾燥による中途覚醒を防ぎます。
アロマディフューザーでは、ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のある精油を使用し、嗅覚を通じて副交感神経を優位にします。
これらのアイテムを上手に活用することで、より快適で質の高い睡眠環境を作ることができます。ただし、個人の好みや体質に合わせて選択することが重要です。
睡眠サプリメントの活用
日本では医薬品として処方される場合があります。体内時計の調整や入眠困難の改善に効果が期待できますが、医師の指導のもとで使用することが重要です。
- 自己判断での長期使用は避ける
- 他の薬との相互作用に注意
- 14歳以下の小児、妊娠・授乳中の女性は使用を控える
メラトニン製剤を使用する際の注意点は、安全性を最優先に考慮する必要があります。
自己判断での長期使用については、メラトニンは自然に体内で産生されるホルモンであるため比較的安全とされていますが、外部からの長期補給により体内での自然な産生能力が低下する可能性があります。また、適切な用量や使用期間については個人差があるため、医師の指導のもとで使用することが重要です。
では、特に血圧降下薬、抗凝固薬、免疫抑制薬との併用時には注意が必要です。メラトニンがこれらの薬物の効果に影響を与える可能性があるため、現在服用中の薬がある場合は必ず医師に相談してください。
使用を控えるべき対象については、小児では体内でのメラトニン産生システムがまだ発達途中であり、妊娠・授乳中の女性では胎児や乳児への影響が完全に解明されていないため、使用を避けることが推奨されています。
サプリメントに頼る前に、まずは生活習慣の改善や睡眠環境の整備から始めることをお勧めします。根本的な改善が最も効果的で安全な方法です。
FAQ
Q1: 毎日何時に寝るのがベストですか?
個人差はありますが、メラトニンの分泌が始まる時間を考慮すると、22時~24時の間に就寝するのが理想的です。重要なのは毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計を安定させることです。
Q2: 寝つきが悪い時はどうすれば良いですか?
30分以上眠れない場合は、一度ベッドから出てリラックスできる活動(読書、軽いストレッチ、温かい飲み物など)を行い、再び眠気を感じたらベッドに戻りましょう。無理に寝ようとすると、かえって緊張状態が続いてしまいます。
Q3: 夜中に目が覚めてしまうのはなぜですか?
加齢、ストレス、カフェインの摂取、睡眠環境の問題などが原因として考えられます。規則正しい生活リズム、適切な睡眠環境の整備、ストレス管理を心がけることで改善が期待できます。
Q4: 昼寝は睡眠の質に影響しますか?
15時以降の昼寝や30分以上の長時間昼寝は、夜の睡眠に悪影響を与える可能性があります。昼寝をする場合は、15時までに20分以内に留めることが重要です。
Q5: コーヒーは何時まで飲んで大丈夫ですか?
カフェインの作用時間を考慮すると、就寝4~6時間前(午後3時頃)以降はカフェインの摂取を控えることをお勧めします。個人差があるため、睡眠への影響を観察しながら調整してください。
Q6: 睡眠薬を使わずに改善する方法はありますか?
生活習慣の改善、睡眠環境の整備、ストレス管理、適度な運動など、非薬物的なアプローチで多くの睡眠問題は改善可能です。ただし、症状が続く場合は医師に相談することをお勧めします。
参考文献
- メラトニン - Wikipedia
- 睡眠 - Wikipedia
- 睡眠不足 - Wikipedia
- Healthy Sleep | MedlinePlus
- Effect of melatonin supplementation on sleep quality: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials - PubMed
- Meta-analysis: melatonin for the treatment of primary sleep disorders - PubMed
- Non‐pharmacological interventions for sleep promotion in the intensive care unit
- Sleep Deprivation and Energy Balance - ClinicalTrials.gov
- ドクターナウは特定の薬品の推薦および勧誘を目的としてコンテンツを制作していません。ドクターナウ会員の健康な生活をサポートすることを主な目的としています。 * コンテンツの内容は、ドクターナウ内の医師および看護師の医学的知識を参考にしています。
風邪や目の乾きなど、自宅でお薬を受け取れる

